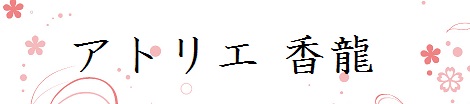作品
つひにかも嘆き透れば一点の晶となりてやいのち光らん
つひにかも嘆き透れば一点の晶となりてやいのち光らん 作者:岡本かの子 『わが最終歌集』(昭和4年)所収 作者は17歳で与謝野晶子に師事し、5冊の歌集を残しました。小説家として昭和11年~わずか3年間で驚異的に活躍するも、 […]
始制文字 智永の千字文を臨書
智永(南北朝時代)梁に生まれました。 智永が書いた千字文を臨書しました。 始制文字 読み方:はじめてもじをせいし。 意味:始めて文字をつくりました。 下記は智永の文字
うたたねに恋しき人を見てしより夢てふものはたのみそめてき
うたたねに恋しき人を見てしより夢てふものはたのみそめてき 作者:小野小町 口語訳:うたたねをした時に、恋しい人を夢に見てからは、(それまで頼りにならないと思っていた)夢というものを頼みにおもうようになった。 頼りにならな […]
験なきものを思はずは一杯の濁れる酒を飲むべくあるらし
験なきものを思はずは一杯の濁れる酒を飲むべくあるらし 作者:大伴旅人(665~731)万葉集 現代語訳:(思っても)かいのないもの思いをしないで、一杯の濁り酒を飲むの方が良いようだ。 香龍撮影 八海醸造(新潟 魚沼の里)
海かん河淡 智永が書いた千字文を臨書
智永(南北朝時代)梁に生まれました。 智永が書いた千字文を臨書しました。 海かん河淡 ⇒ 「かん」の字が変換できませんでした🙇 読み方:かいかんかたん 海はしほからく、河は淡い。。 意味:海の水は塩 […]
ちぎれつつ吹きとぶ雲も夕焼し
ちぎれつつ吹きとぶ雲も夕焼し 作者:山口青邨 (1892年~1988年 岩手県盛岡市) 季語:夕焼し(夏) 現代語訳:散り散りになりながら吹き飛んでいく雲も夕焼けに染まっていく 香龍撮影
菜重芥薑 智永が書いた千字文を臨書
智永(南北朝時代)梁に生まれました。 智永が書いた千字文を臨書しました。 菜重芥薑 読み方:さいちょうかいきょう。さいはかいきょうをおもんず。 意味:果物は、すももとからなしが珍しく、野菜はからしなとショウガを重ん […]
天つ風雲のかよひぢ吹き閉ぢよをとめの姿しばしとどめむ
天つ風雲のかよひぢ吹き閉ぢよをとめの姿しばしとどめむ 作者:良岑宗貞(よしみねのむねさだ)は僧正遍昭の出家前の名前。 口語訳:空を吹く風よ。(この天女たちが帰ってゆく)雲の中の通り道を吹き閉ざしてくれ。 (この美しい)天 […]